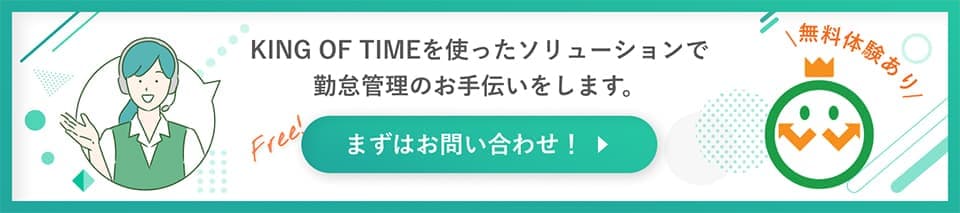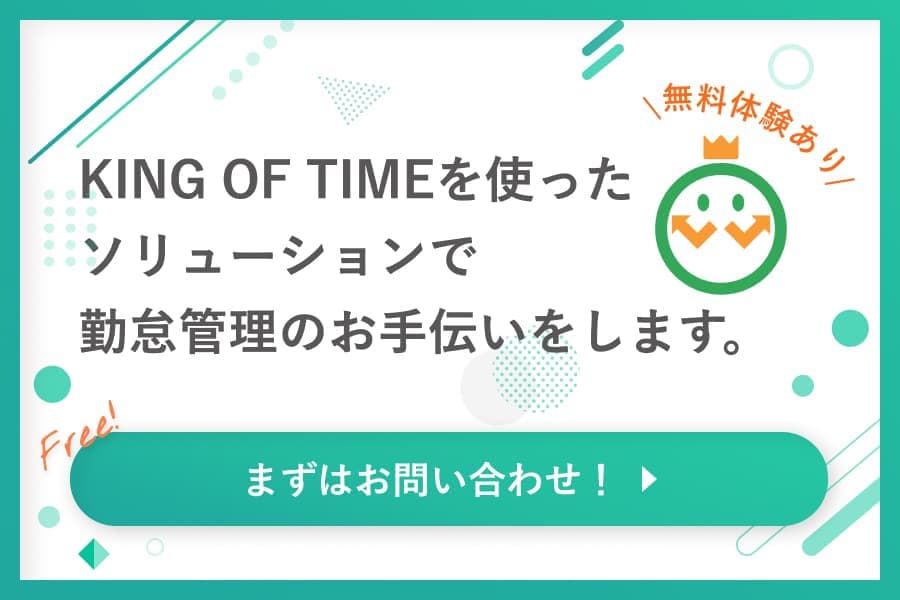2024.5.30
日本でも関心の高い「始業時間」について改めて考えてみましょう

今回は、日本でもたびたび話題となっている「始業時間」について取り上げます。そもそもの労働時間の考え方をおさらいするとともに、タイで判断する際の基準を具体的に解説していきたいと思います。
始業時刻の取り扱いについては、労働関連のトラブルの中でも関心が高い事項です。日本では最近の労務トラブル、特に残業代の未払い問題において、実務面でどの時間から始業時間(労働時間開始)として取り扱うのかという点が課題となっています。
日本の労働基準法での考え方は?
まずは労働時間の考え方からおさらいしていきましょう。
基本的に日本でもタイでも原則の考え方に大きな違いはありません。日本では、過去の裁判例や厚生労働省のガイドラインなどに基づいて、労働時間とは、客観的に見て「使用者の指揮命令下に置かれている」状態のことを指すとされています。
使用者の指揮命令下にあるか否かについては、その行為が会社から「義務付けられているか」もしくは「黙示や明示の指示により余儀なくされているか」などから、業務性、待機性、義務性の観点で個別具体的に判断されます。また、客観的というのは、就業規則や労働契約などで定められているかどうかではなく、実態で判断されることになります。

タイの労働者保護法(判例等)考え方を確認してみましょう
一方、ではどうでしょうか。タイの法律を厳密に解釈すると、始業の前は「業務時間外であり会社の命令下に置かれていない時間」となります。日本でも使用者の指揮命令下にあるか否かが判断の基準とされていますので、おおむね日本と同じような認識だと言っていいでしょう。
始業前の朝礼はすべて違法なの?
具体的な例でいうと始業時刻の取り扱いで線引きが難しいのは、朝礼などではないでしょうか。
始業時刻の9時に間に合うように、8時50分から朝礼をするのは違法なのでしょうか?
始業前に朝礼をすることは、それだけで直ちに違法となるものではありません。ただし、その朝礼への参加を必須としたり、朝礼に遅刻した際に注意や罰則を与えたりすることは違法となります。そのようにしたい場合には、朝礼を始業時刻以降に行うこととしなければなりません。
トラブルが起きる前に対策しておきましょう

今回触れた例に合致はするけれども、これまで慣習としてやってきたし特に従業員からも何も言われていないから大丈夫……と思っていませんか?
日本でも以前は始業時間が曖昧であったり、労働時間を5分単位、10分単位で丸めて集計することは当たり前のように行われてきましたが、最近はコンプライアンスの観点からも正しい運用に切り替えを進めている企業が多くなりました。
タイではまだ「解雇を中心とした労務トラブル」が多いのは事実ですが、今後労働者の意識も変わってくるでしょう。
対策を後回しにしてしまった場合、損害賠償請求されるなどの金銭的なリスクはもちろんですが、最近では従業員がSNSに企業の労務管理が不十分だと書き込むケースが見られます。こういった書き込みが意図せず拡散されてしまうと、人材の確保だけでなく企業の経営自体にも影響を与える可能性があります。
これまで慣習としていたものについても、改めて会社として対策を検討していくことが望ましいでしょう。
慣習を今一度見直したうえで、就業規則に始業前の出勤や準備などについて記載して周知しておくことをお勧めします。
どのように管理するのが望ましいの?
始業前に参加が必須の朝礼などをすることはトラブルのもと、とお伝えしてきました。しかしそれ以外にも、始業時刻に関するお悩みとして以下のようなケースが挙げられます。
Aさん:9時始業としているが、朝の通勤ラッシュがいやだからと8時に出勤し、打刻している。始業時刻まではコーヒーを飲んだり、新聞を読んだりしていて労働はしていない。
Bさん:9時始業としているが、顧客からの要望があったため8時から商談をする。
AさんとBさんもどちらも8時からオフィスにいるという点では同じですが、Aさんは労働していません。しかし打刻はしているため、8時からの時間が労働時間として集計されています。
企業の人事総務担当者の皆さまとしては、「Aさんは労働時間ではなく、Bさんは労働時間」として取り扱いたいのではないでしょうか。
クラウド勤怠管理システムKING OF TIMEでできること
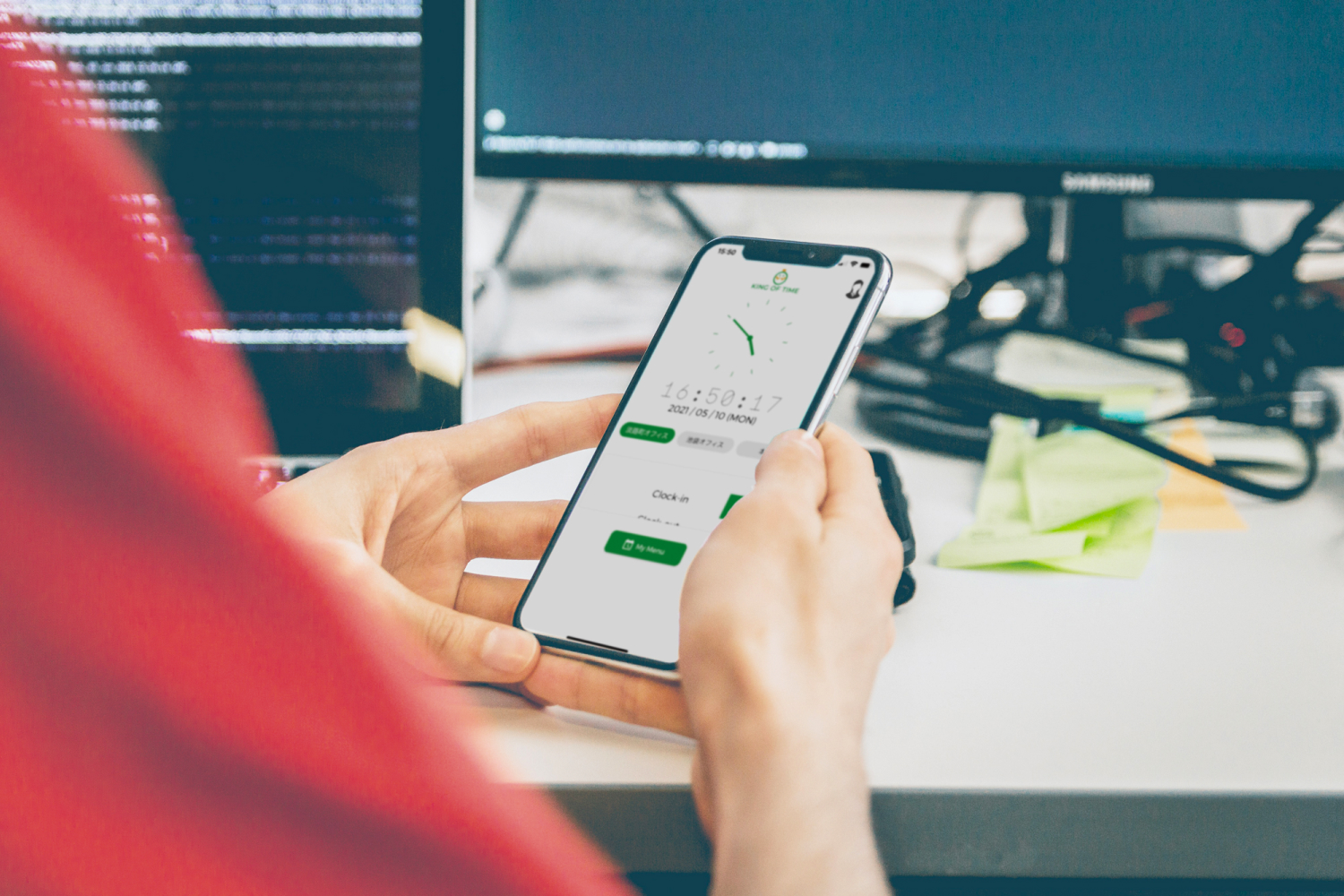
そこでお勧めしたいのが、KING OF TIMEの「始業時刻前の勤務を申請制とする」機能です。
始業時刻の9時以前に打刻をしていたとしても、申請がなければ労働時間として集計しないことができます。Bさんのように本当に働いている場合には申請させることで、労働時間として集計することが可能です。
仮にAさんのように労働していないにも関わらず申請してきた場合には、その申請を棄却することができます。棄却時に管理者から棄却の理由を記入することで、どのような理由で認められなかったかを明記しておくことが可能です。
このような制度や機能はたしかに有効ですし便利ですが、導入するだけでは意味がありません。
きちんと従業員へ周知し、管理者からも継続的な声かけをしていくことで、企業の風土として根付かせていくことも大切です。