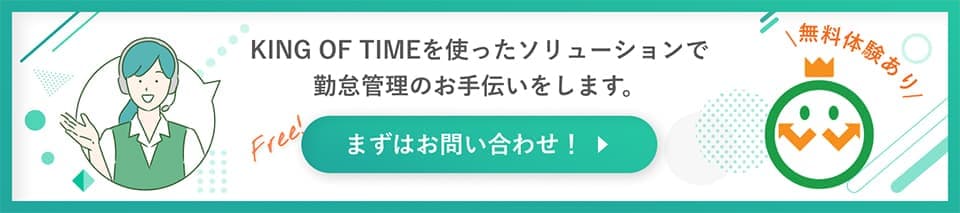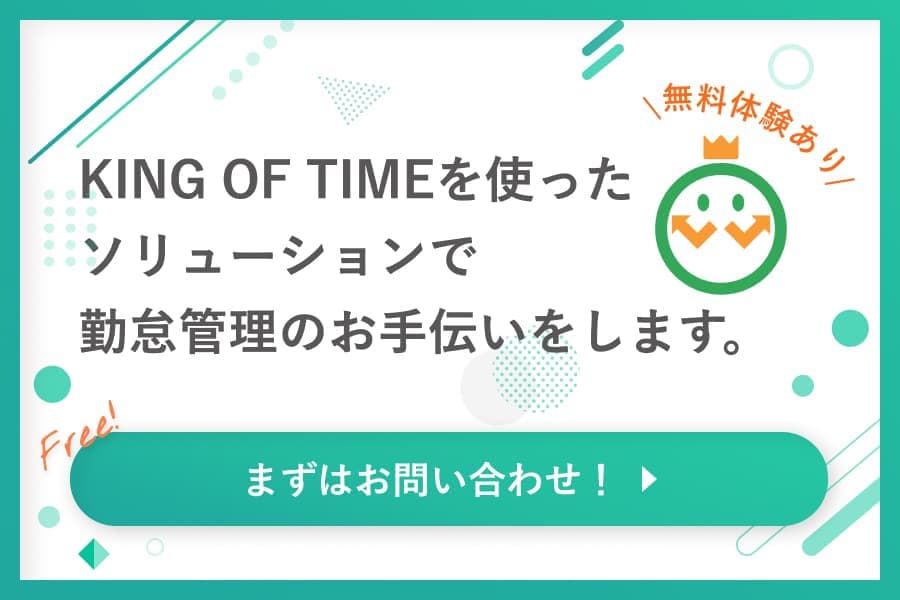2025.11.6

日本企業がタイに進出して数十年が経ち、製造業からサービス業まで幅広い分野で日系企業が活躍しています。
しかし、現地での労務管理や人材育成に携わると、必ずといってよいほど直面するのが「働き方の違い」が原因のすれ違いです。
日本では当たり前とされる「責任感」「時間感覚」「報連相(報告・連絡・相談)」といった常識が、タイにおいては必ずしも同じ意味を持ちません。
結果として、評価制度の行き違い、業務遅延、トラブル発生時の情報共有不足などが起こりやすくなります。
第1回目でタイ赴任1年目に押さえておきたいタイの文化的背景を踏まえた労働環境でも少し触れましたが、今回はさらに深掘りし、日タイ間での働き方のすれ違いをいかに克服できるかを探っていきます。
すれ違いが頻発する現場と管理上の注意点
「責任感」の意味が違う?-日本とタイの「責任感」の定義の違い
日本企業で言う「責任感」とは、与えられた業務を単にこなすだけでなく、状況に応じて主体的に判断し、最終的に成果を出すまでやり抜く姿勢を含みます。
さらに、自分の担当範囲を越えても組織全体に貢献することが求められる場合が多いでしょう。
一方、タイでは「責任感」という言葉が意味するのは「与えられた役割やタスクをきちんと遂行すること」にとどまるケースが多く見られます。
つまり「自分の仕事を終えたら責任は果たした」と考える傾向が強いのです。
たとえば、顧客からクレームがあった場面を想定してみます。
日本人の感覚では「顧客の問題が解決するまで全体の責任で対応すべき」と捉えますが、タイ人スタッフの中には「自分の担当外の問題は関係がない」、「別の部署の責任」と線引きをしてしまう場合があります。
その結果、顧客対応が遅れ、更なる損失を生む可能性につながることもあります。
この違いというかズレを「責任感が足りない」と単純に評価してしまうと、タイ人従業員の士気を下げてしまい、逆に「日本人上司は要求が過剰だ」と不信感を抱かれるリスクがあります。
したがって、「責任感」という言葉の定義自体が日本とタイでは異なることを理解し、その差を埋める説明や教育が必要となります。
時間感覚のギャップ
日本の企業文化においては「納期厳守」「定刻遵守」は基本中の基本です。
会議は開始5分前に全員が着席し、納期も必ず守ることが当然とされています。
その背景には、日本社会が重んじる「約束は守る」「時間に正確であることが信頼につながる」という価値観があります。

一方、タイでは「サバーイ(気楽に)」という考え方が生活全般に根付いており、時間の使い方も柔軟です。
会議の開始時間が多少遅れることや、納期を「目安」として捉えることは一般的であり、それが相手に対する不誠実さを意味するとは必ずしも考えられていません。むしろ「柔軟に対応すること」や「人間関係を優先すること」が重視されます。
例えば、工場での納期対応においても、日本人は「予定より前倒しで仕上げる」ことを目指す一方、タイ人スタッフは「期限内に収めれば問題ない」と考える傾向があります。
さらに、渋滞や突発的な家庭事情による遅刻も、タイでは比較的寛容に受け止められますが、日本人はこういったことを「ルーズ」と評価してしまいがちです。
しかし、「タイは時間に関しては寛容なので…」と認めてしまお、このギャップを放置すると、納期の遅延や業務効率の低下につながり、最終的に顧客満足度や会社への信頼にも影響します。
したがって、タイで仕事を進める際には「期限の前倒し設定」や「複数回のリマインド」をルール化するなど、時間管理を仕組みでカバーする必要があるのです。
報連相の誤解
日本企業では「報告・連絡・相談(報連相)」が仕事の基本行動として徹底されています。
問題が起きればすぐに上司へ報告し、必要な連携を取ることが当然とされ、それが評価にも直結します。
しかしタイでは、報連相に対する意識が大きく異なります。
問題を報告することは「自分の能力不足をさらすこと」と受け止められる場合があり、トラブルが起きても現場で抱え込んでしまう傾向があるのです。
また、上司に「悪いニュース」を伝えることは失礼と感じる従業員も少なくありません。

実際、ある製造業の事例では、機械トラブルが発生していたにもかかわらず、担当者が「報告すれば叱責されるのでは」「報告すると自身の評価が下がるのでは」と恐れて黙っていた結果、修理対応が遅れ、数時間にわたり生産ラインが完全に停止するという事態に発展しました。
日本人からすれば「なぜすぐに報告しないのか」と不思議に思う場面ですが、タイ人側にとっては「問題を自分の中で解決しようと努力すること」が責任感の表れと理解されていたのです。
さらに、タイの文化では「相手にネガティブな情報を直接伝えること」を避ける傾向が強いため、報連相が形式的なものにとどまり、実際には重要な情報が共有されないまま物事が進んでしまうこともあります。
このギャップを解消するためには、「報告は問題を指摘することではなく、チーム全体を守る行為である」という価値観を繰り返し説明し、「報告した従業員を評価する仕組み」を取り入れることが有効です。
対応策と実務的な運用
1. ルールと柔軟性の両立
まず前提として、就業規則や労働時間管理は、タイ労働者保護法をベースに整備することが欠かせません。
さらに、日本人管理者自身が「自社の就業規則にどのような内容が記載されているのか」「会社内の規定はどのように運用されているのか」を周知し、理解することが重要です。
ルールは存在していても、管理者が正しく理解していなければ、正しく運用することが難しくなります。
その上で、納期管理や会議時間の運用には「柔軟性を持たせる工夫」が効果的です。
たとえば、納期は「必ず守るべきもの」と強調しながらも、社内の進行管理では数日の「余白期間(バッファー)」を設定しておく。
会議についても、予定時刻前にリマインドを送信する、遅刻者に対しては厳しく叱責するのではなく「次回は余裕を持って来てほしい」と柔らかく注意をした上で、就業規則に則って、回数に応じて警告書を発行する。
このように「ルールの明確化と柔軟な運用の両輪」で進めることが、現地スタッフにとっても受け入れやすく、かつ業務の安定化につながります。

2. コミュニケーション研修の実施
日本企業文化で重視される「報連相(報告・連絡・相談)」を、タイの職場にそのまま導入すると、かえって逆効果になる場合があります。
先に述べた通り、タイ人スタッフにとって「問題を報告すること=自分の失敗を晒すこと=自分が能力が低いと開示すること」と受け止められがちだからです。
その結果、トラブルを隠し持ち、発覚が遅れて被害が拡大する事例は少なくありません。
したがって、研修や日常のマネジメントにおいては「報告は処罰の対象ではなく、むしろ信頼を高める行為である」と明確に伝える必要があります。
例えば、
「問題が起きたら必ず共有することが自分を守ることにつながる」
「早期報告は、チーム全体を救う行動である」
「報告したことによって評価が下がることはない」
と繰り返し説明し、安心して報告できる心理的安全性を整えることが大切です。
さらに、報告を行ったスタッフを「プラスに評価する文化」をつくることも有効です。
たとえば、問題を素早く共有したことで被害を最小化できた場合、そのスタッフを会議の場で称賛したり、評価や査定自体に加点するなどが効果的です。
これにより「報告することはプラスである」という意識が定着しやすくなります。
3. 管理職の心構え
日本人駐在員や管理職にとって何より重要なのは、「自分の経験や常識が世界の常識ではない」という認識です。
日本で育った価値観をそのまま現地に当てはめると、スタッフとの間に摩擦が生じやすくなります。
これはタイだけではなく、どこの国でも同じですが…。
タイ人スタッフは「家族や生活を大切にしながら働く」という価値観を持つことが多く、日本的な「会社への献身」や「長時間労働=美徳」といった考え方とは異なります。
したがって、管理職はタイ人スタッフの文化的背景を尊重し、「彼らの価値観に合った動機付け」を意識する必要があります。
そのうえで、日本式の「改善意識」「品質へのこだわり」「顧客志向」といった強みを少しずつ取り入れていく「ハイブリッド型マネジメント」を実践するのが理想です。
つまり、双方の価値観を組み合わせ、「タイ流の柔軟性」と「日本流の継続的改善」を両立させるスタイルです。
それが熟成され、「企業文化」として根付いていくと考えます。
4. 社内体制の構築
最後に、文化ギャップを個人の力量や仕組みではなく特定の人の能力や経験に依存したやり方に頼らず、「仕組みとして解消する社内体制づくり」が不可欠です。
具体的には以下のような取り組みが考えられます。
①二言語でのマニュアルと規則の整備
会社にある業務マニュアルや規則・規程は、すべて日本語とタイ語で整える必要があります。
現場で誰もが理解できる状態にし、イラスト、写真、フローチャートなども利用し、どのレベルでも理解できるのが理想です。
②定期的な1on1ミーティングによる進捗確認
上司と部下が1対1で話す時間を設け、業務進捗だけでなく困りごとや不満も吸い上げます。
特にタイ人管理職に関しては、上司である日本人を通じて会社の意向を伝え、教育する場にもなります。
また報告の遅れや不満の蓄積を防ぐことができ、情報収集にも役立ちます。
③労働法研修の実施
日本人駐在員向けには「タイ労働法の基礎知識」を、タイ人スタッフ向けには「会社規定と権利義務の理解」をテーマにした研修を実施します。
(筆者は労働法の講師でもあります)
これにより、双方が共通の法的土台を持つことができ、労務トラブルを未然に防止できます。
このように、「制度として文化的ギャップを吸収する仕組み」をつくることで、担当者や管理職の力量や感情に左右されない安定した運営が可能になります。

まとめ
日タイ間の働き方のすれ違いは、「責任感」「時間感覚」「報連相」という基本的な要素において顕著に表れます。
その背景には文化や価値観の違いがあり、単に「タイ人の問題」と捉えるのではなく、マネジメント側である日本人の理解不足として捉えることが重要です。
タイ労働法に即した制度整備と運用、文化的背景を理解した柔軟な運営、そして日本人管理職自身の意識改革。
この三点を押さえることで、日タイ間の働き方のギャップはむしろ「多様性を活かす強み」に変えられると思います。
最終的な提言としては、「コンプライアンス」「異文化理解」「仕組みづくり」の三本柱をベースに、タイ人スタッフとの信頼関係を築くことが、長期的な事業の成功につながるといえるでしょう。
本日のコラムがご参考になれば幸いです。
執筆者:前田千文
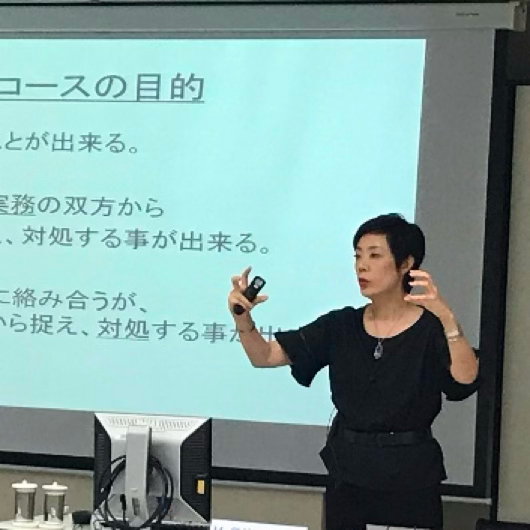
2001年1月、TJ Prannnarai Recruitment創業。2015年より泰日経済技術振興協会にて労働法の講師を拝命。2025年7月、アベノ印刷の2代目社長に就任。