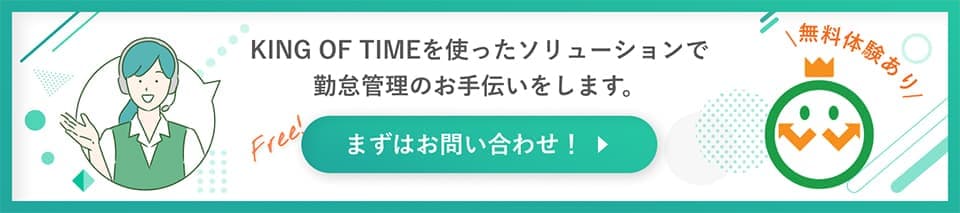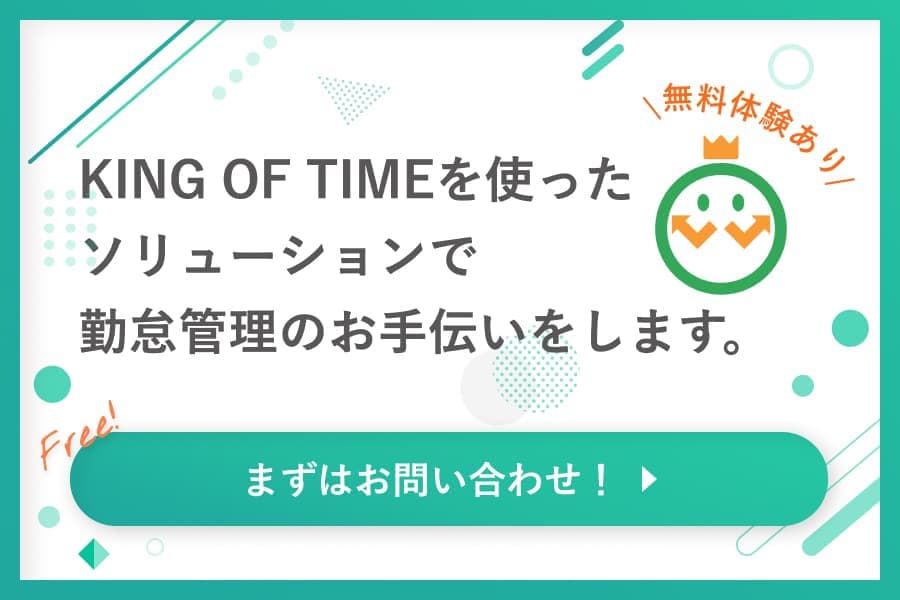2025.8.29
― 表面のYESと内面の本音、そのギャップにどう対応するか?
こんにちは。前田千文です。
1998年5月にタイに来てから、早27年が経ちました。
タイに来て最初の数年間、私は「タイ人のYES」に悩まされた経験があります。
タイ人の「YES」はYESではない??

「はい、わかりました」
この一言で、安心して業務を任せたはずなのに、なぜか結果が伴わない。
期限になっても出てこない。
実は終わってないどころか、何もやってなかった。
なぜ?なぜ??
タイで働く多くの日本人管理職が一度は経験する、この不思議な感覚。
タイ人スタッフが口にする「YES」には、日本人の「了承」や「理解」とは少し違うニュアンスが隠されているようです。
その背景には、タイの文化、価値観、そして「マイペンライ(ไม่เป็นไร)」の精神が深く根付いています。
今回、タイ人スタッフがなぜ「YES」と言うのか?
どうして意図が伝わらないのか?
そしてそのギャップをどう埋めていくべきか?
この疑問につき、読み解いていきたいと思います。
タイ人の「YES」に隠された本音とは?
タイ人の「YES」は、必ずしも日本語の「はい」と同義ではないようです。
表面的には肯定していても、内心では「理解していない」「できない」「やりたくない」と思っているケースが少なくありません。
それでもなぜ「YES」と言うのか?
それは、人間関係を壊さないための配慮らしいのです。

タイ人スタッフの「YES」表現と実際の意味
以下は、タイ人スタッフの「YES」という返答と、実際の意味と本音を表した表です。
| 日本語での反応 | 英語表現 | タイ語表現 | 実際の意味・本音 |
| はい、わかりました | Yes, I understand. | ครับ/ค่ะ เข้าใจแล้ว (カップorカー、カウチャイレオ) | 実はよくわかっていないが、聞き返すのが気まずい |
| 大丈夫です | No problem. | ไม่เป็นไร (マイペンライ) | 問題がある可能性もあるが、相手に気を遣って言わない |
| やっておきます | I will do it. | จะทำให้ครับ/ค่ะ(ジャ・タームハイ/カップorカー) | 本音では難しいが、断ることが失礼にあたると考えている |
| はい(曖昧に) | Yes… | ครับ/ค่ะ… (カップorカー) | はっきり断ると関係がこじれるので、とりあえず同意したフリをしている |
このような曖昧な同意表現は、日本人からすると「なぜ本当の事を言ってくれなかったのか?」「できないなら、できないと言って欲しい」と感じる原因になりますが、タイ人にとっては「波風を立てない処世術」なのです。
「マイペンライ」の精神と問題回避文化
「マイペンライ(ไม่เป็นไร)」は、タイ人がよく使う言葉ですが、その背後には「物事を穏やかに受け入れ、問題を深刻化させない」という価値観が存在します。
意味として広く理解されているのは「問題ない」「大丈夫」という意味なのですが、それ以外にも以下のような意味で使われることがあります。
(例)レストランのスタッフがお水をこぼしてしまい、お客さんに水をかけてしまった。
「マイペンライ」=たいしたことはありません。=やはり問題ない?
日本人的には、そこは「ごめんなさい」でしょ?(モヤモヤ…)
「マイペンライ」に含まれる問題回避の考え方の背景としては、
・ 問題があっても過度に追及せず、「次がんばろう」という前向きな気持ち
・ 感情を表に出すことを避け、調和を大切にする
・ 自然との共生を重んじる農耕文化、仏教の無常観からくる「あるがままを受け入れる」哲学
この考え方があるからこそ、「できない」とは言わずに、まずは「YES」と受け入れ、やり過ごすという文化が生またようです。

異文化マネジメントで必要な3つのポイント
タイ人の文化的な背景を知った上で「あー、そうですかー」とできないのが仕事をする上で辛いところです。
タイ人への理解や歩み寄りは必要だとは思うのですが、全てを受け入れるわけにはいきません。
そこで、タイ人スタッフの「YES」を鵜呑みにしないためには、文化の違いを理解した上で、対話の工夫を重ねる必要があると考えています。
今日は3つご紹介したいと思います。
ポイント1.:再確認の徹底と再言語化
「わかりました」だけでは不十分というのがわかった上で、以下のように、自分(タイ人スタッフ)の言葉で説明してもらうプロセスが重要です。
・「どうやってやる予定ですか?」と尋ねて再度説明させる。
・図・フロー図・写真で可視化する。
・納期・責任者・優先順位を明確にして複数名で共有する。
ポイント2.:「叱責」よりも「相談・共感」
タイでは人前で怒ることは、「相手の顔を潰す」行為と見なされます。
そのことを踏まえ、
・できるだけ個別に呼び出して話す。
・「どうしてうまくいかなかったと思う?」と原因を一緒に探る。
・「どうやったら上手く行ったと思う?」と次のオプションを一緒に探る。
・次回に向けて「チャンス(=逃げ道)」を与える。
そういえば、タイ人経営者の先輩が言っていました。
「タイ人を叱るなら、先に逃げ道を作ってあげるのが“徳”なんだ」と。
ポイント3.:なぜ、その業務が必要なのかを説明する
タイの若い世代ほど、「目的」や「意義」を重視します。
よって、
・「なぜこの手順が必要か」を簡潔に説明する
・「お客様の信用に関わるから」など、仕事の意義を伝える
・できれば、本人の利益に結びつける(例:成果給・評価)

おわりに ― 共に働くために必要なのは「YESの先」を見ること
タイ人スタッフの「YES」は、時に信頼を裏切るように感じられるかもしれません。
しかし、それは彼らが人間関係を大切にし、対立を避けたいという文化的配慮の表れでもあります。
日本人のマネジメントスタイルを押し付けるのではなく、相手の文化を理解した上で歩み寄る…。
その上で、こちらの要望を伝える…
それが、タイという国で信頼を築き、成果を出すための第一歩ではないかと思います。
タイで27年を過ごした私の経験から言えるのは、「YES=了承」ではないというシンプルな事実が、マネジメントの質を大きく左右するということです。
大切なのは、「YESと言ってくれた」ではなく、「本当に理解しているかどうか」「実行できるかどうか」「実行しているかどうか」「結果はどうなったか?」にまで目を向けること。
そして、文化を背景にした違いを否定せず、相互理解を深める姿勢を持つことだと考えます。
皆さんの現場でも、ぜひ一度、「YESの裏にある本音」に思いを馳せてみてください。そこに、より良いチームづくりのヒントがあるはずです。
今日の話題が皆様の日々のお仕事に活かしていただければ幸いです。
執筆者:前田千文
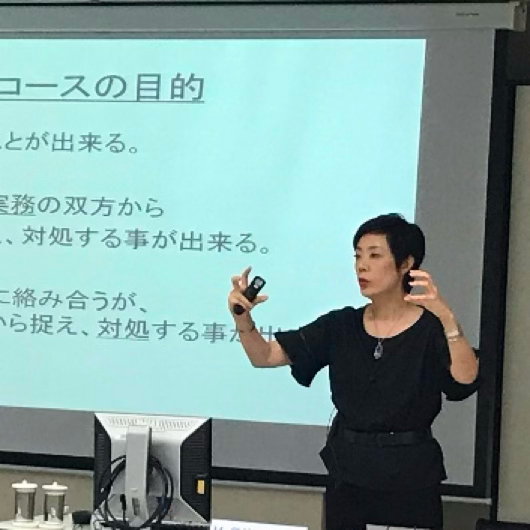
2001年1月、TJ Prannnarai Recruitment創業。2015年より泰日経済技術振興協会にて労働法の講師を拝命。2025年7月、アベノ印刷の2代目社長に就任。